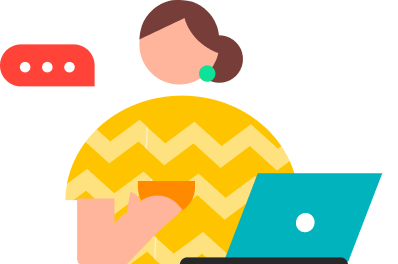Çeşitli İngilizce öğretmenleri arasından arama yapın...
Michael
「措くあたわざる」という言葉
おくあたわざるというのは「絶えず」という意味を現すと解ってきましたが、「措く」と「あたわざる」の語源は何でしょうか。
また、勿論、「措く」の意味分かりますけれど、何故それが「あたわざる」と一緒になっているか全然分かりません。因みに、「おくあたわざる」の意味合いは「絶えず」と些細で異なるなら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
18 Ara 2009 18:33
Yanıtlar · 2
「措く能わざる」は動詞「措く」+「能う(あたう)」+否定「ず」です。
意味はnoriさんの書かれている通りですで、
この場合は
「措く」=何かから心を隔てる→やめる、しないでいる
ですね。
「能う」は「できる」という意味で、古い言葉では「能ふ」とも書きます。「~することができる」と言いたいときは、その動詞の辞書形+「こと」に続けますが、「こと」は省略される時が多いです。
(例)
食べることができる-食べる(こと)能う
措くことができる-措く(こと)能う
否定「ず」は、古い言葉で「行かない」「食べない」などの「ない」と同じ意味です。名詞の前につくとき「ざる」に変化します。
(例)行かない人-行かざる人
食べないこと-食べざること
まとめ
「措くあたわざる」=やめる/しないでいることができない
19 Aralık 2009
措く能わざる(おくあたわざる)ですよ。書面語でよく使いますね。
措くの意味は難しいです。日本人でも時々間違えています。
措く ①置く ②心を隔てる、警戒する、
能わざる ①できない
・「措く能わざる」本=本を①置く(読むのを止める)ことができないくらい面白い
・「尊敬/信頼措く能わざる」=尊敬/信頼から心を隔てることはできない=尊敬、信頼せずにはいられない
心理面で措く能わざるを使うときは二重否定になる、
それ以外は読書の面だけ違うように読む(これ以外の用法はほとんど見ない)
って感じです。
19 Aralık 2009
Hâlâ cevap bulamadın mı?
Sorularını yaz ve ana dil konuşanlar sana yardım etsin!
Michael
Dil Becerileri
Çince (Mandarin), İngilizce, Japonca, Rusça
Öğrenim Dili
Çince (Mandarin), Japonca, Rusça
Beğenebileceğin Makaleler

Santa, St. Nicholas, or Father Christmas? How Christmas Varies Across English-Speaking Countries
3 beğeni · 0 Yorumlar

Reflecting on Your Progress: Year-End Language Journal Prompts
2 beğeni · 0 Yorumlar

Same Word, Different Meaning: American, British, and South African English
25 beğeni · 17 Yorumlar
Daha fazla makale