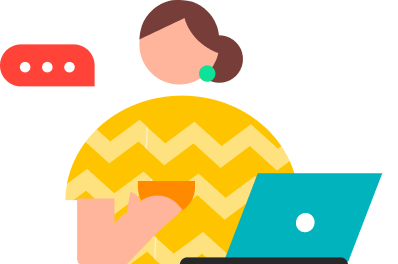Выбрать из множества учителей по предмету английский...
Ryoko
Репетитор сообщества日本人ですが日本語について質問させてください。
以下の助詞「に」について教えてください。
まだ泳ぐには寒すぎる。
このカレー子どもが食べるには辛すぎる。
取るに足らない。
これらは格助詞でしょうか。「動詞の連体形 + に」で正しいですか。文法的にはどのように解釈すれば良いでしょうか。
勉強しに行く / 映画を見に行く / 買い物に行くなど、「連用形 + に」の場合は「目的を表す格助詞」で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
28 февр. 2017 г., 9:31
Ответы · 8
3
そもそも日本語の文法というものは、外国の方に日本語を教えるためにこそ、必要なものなんですよね。私自身、学校にいた頃は「文法なんて知らなくても言葉は喋れる」と考えてろくに勉強していなかったクチなのですが、今になってその態度はとても傲慢だったと思います。
そして外国語話者の方に日本語の構造を伝えるという立場に立った時、私たちが学校で教えられてきた「文法」は極めて不完全で役に立たないケースが多いということが、これまでに多くの学者から指摘されてきましたが、私自身もこのかんとみにそのことを実感させられています。たとえば
①印欧語の「主語/述語」という概念を日本語に当てはめると、「は」と「が」の果たす役割の違いを説明できなくなる。(「は」は主題、「が」は主格を提示する)。
②日本語の動詞の活用形は、ひらがな表記では正確に表現できない。(「書く」という動詞の語幹は「か」ではなく「kak」である)
③形容動詞という概念を作ることに意味はない (日本語教育の現場では、いわゆる形容動詞を「ナ形容詞」それ以外を「イ形容詞」として教えている)
…等々のことは、研究者のあいだではかなり昔から常識になっているらしいのですが、私の知る限り上にあげたいずれの例も、学校教育には採用されていません。私の手元にある「岩波シリーズ 日本語の文法」という本では、助詞や助動詞という概念自体が否定されて「助辞」という用語が使われています。ですから例えば「泳ぐには早すぎる」という文を「動詞の連体形+格助詞」と説明することは、学校のテストでは「正解」になる答えであったとしても、それで果たして外国の人に納得してもらえるのか、という観点から、文の構造を再検討してみる必要があるのだと思います。
だからと言って私自身、上手な答え方ができる自信はありませんが…
例えば「格助詞」の「格」とは、「名詞類が文の中で他の単語に対してとる関係のあり方を示す文法カテゴリ」のことです。英語だとI (私は/が=主格=nominative)、my (私の=所有格=possessive)、me (私を=目的格=objective) といった風に、名詞そのものが変化する形でこの「格」が表現されています。(ロシア語などだとこの「格変化」はさらに複雑で、「〜に」にあたる格は「与格=dative」と呼ばれています)。
これに対し、日本語では名詞の形は変化しません。代わりに「が/の/に/を」などの助辞(助詞)をつけることで「格」を表現する。これが日本語という言語の特徴なのだと言えます。
そしてこのように「格」というものを考えてみたなら、「動詞+格助詞」というような「助詞」の使い方は、そもそもおかしいのです。「格」とは「名詞のあり方」を示す概念だからです。
だからここではむしろ「動詞が名詞化している」ということに注目する必要があると思います。
「砂遊び」「リンゴ売り」などのように、日本語の動詞の「連用形(この用語も、使うべきではないという研究者が多い)」には、「動詞を名詞化する」という役割が持たされています。これで、「に」と結合させることができるようになることは、説明できます。
一方、「泳ぐには早すぎる」「食べるには辛すぎる」といった「連体形」の場合は、これも同じく直前の動詞を名詞化する役割を持った助辞「の」が省略されていると解釈することができます。(泳ぐ の には 早すぎる)。「取るに足らない」はyuichoさんの言われるように古語由来だと思いますが、私にはとりわけ「是非に及ばず」といったような漢文由来の言い方が広がったものであるように思われます。(名詞と動詞が厳密には区別できない場合があるのが、中国語の特徴です。「徘徊」など。それをもひとつの文化として「輸入」してきたのが、日本語の歴史なのだと思います。
…つまり上記のように ①動詞の「連用形」、②「連体形」+「の」、③漢語を使った言い方 …等々を使い分けることで、日本語では「動詞を名詞として扱うことができる」ということがポイントなのだと説明すれば、日本語学習者の方には多少はその「文法的意味」が分かりやすくなるのではないでしょうか。
…長々と喋ってしまいました。おやすみなさい。
1 марта 2017 г.
そうでしたか。私はつい数年まえまでたいして日本語に興味がありませんでした。italkiで個人的に言語交換を始めて、サポートをするにはあまりにも日本語の知識に乏しいことに気づき、勉強中です。始めたころは日本語を教えることがこんなに難しいなんて思ってもみませんでした。
1 марта 2017 г.
Ryokoさんは日本語のサポートをされてるんでしょうか?私も英語習得の手段として、日本語の文法や高低アクセントの規則をぼちぼち勉強しています。「先ず隗より始めよ」とは良く言ったもので、日本語アクセント規則と英語との違いを外国人に説明することで英語の発音が飛躍的に向上しました。
28 февраля 2017 г.
Yuichoさん、コメントをありがとうございました。専門家でなくてもここまでご存知とは頭が下がります。勉強になりました。
28 февраля 2017 г.
この場合の「に」は行為の目的を表す格助詞です。通常は「動詞の連用形+に」「動詞の連体形(終止形)+には(「は」は副助詞)」のように使われます。「取るに足らない」は古語由来の諺なので、文法的には例外と考えます。国語の専門家ではないので、飽くまでも私個人の認識です。
28 февраля 2017 г.
Все еще не нашли ответы?
Напишите свои вопросы, и пусть вам помогут носители языка!
Ryoko
Языковые навыки
английский, французский, японский, испанский
Изучаемый язык
французский, испанский
Статьи, которые тебе могут быть интересны

Santa, St. Nicholas, or Father Christmas? How Christmas Varies Across English-Speaking Countries
5 нравится · 4 Комментариев

Reflecting on Your Progress: Year-End Language Journal Prompts
3 нравится · 2 Комментариев

Same Word, Different Meaning: American, British, and South African English
25 нравится · 18 Комментариев
Еще статьи