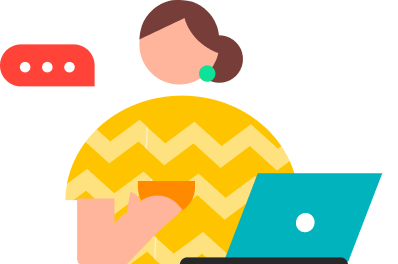Search from various English teachers...
Lee
手紙などは挨拶としてよく季節か天気のことから始まります。どうしてですか?
「厳きびしい 残暑ぎんしょが 続つづいておりますが」
「寒さむさひとしお 身みにしみる 今日きょうこのごろ」
こういう表現は手紙の始めでよく見ます。文化の違いですが、どうしてその表現が必要なのか分かりません。もしかして日本の歴史の文化に繋がっているでしょうか?起源は何でしょうか?説明してくれる方が居れば、うれしくて、ありがたいです!
Apr 14, 2016 12:05 AM
Answers · 2
2
まず、これは時候の挨拶と呼ばれています。
正確かどうかは定かではありませんが、日本は世界的にみても四季(春夏秋冬)がはっきりとしている国です。そのため、日本人、日本の民族は長い歴史の中で自然と季節に対する感性が強くなっています。現在でも、春にはお花見、夏は・・・とその季節を代表する風物詩のようなものがあります。
古くは平安時代、清少納言という歌人の歌(枕草子)にも四季のことが詠まれています。春はあけぼの・・・、夏は夜・・・、秋は夕暮れ・・・、冬はつとめて・・・
実際のところ、時候の挨拶をいれたほうが本題に入りやすい側面もあるので、ワンクッションの機能もあるように思います。
April 14, 2016
"時候の挨拶"と呼ばれる手紙の書き方は、ある程度の知識がないと書きづらいものがあります。
「ちゃんとした時候の挨拶が書ける」=「一般的な教養が備わっている」という印象を与えることができるため、自分の経歴をあれこれと書き並べることなく、相手に一定の信頼を与えることができるツールと考えればいいと思います。たとえば誰かに仕事をまかせる場合、時候の挨拶が書ける人と、書けない人がいれば、時候の挨拶が書ける人の方がチャンスが大きい可能性があります(もちろん、それだけでは決まりませんが)。
April 14, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Lee
Language Skills
Chinese (Mandarin), Dutch, English, French, German, Japanese, Korean, Spanish
Learning Language
Dutch, German, Japanese, Korean, Spanish
Articles You May Also Like

Same Word, Different Meaning: American, British, and South African English
18 likes · 16 Comments

How to Sound Confident in English (Even When You’re Nervous)
15 likes · 12 Comments

Marketing Vocabulary and Phrases for Business English Learners
13 likes · 6 Comments
More articles